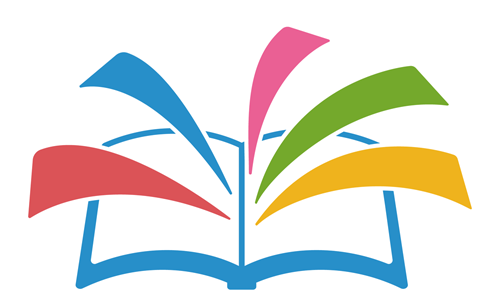 教育の特徴
教育の特徴
「一人でするのを手伝う」自立を大切にする教育
モンテッソーリ教育は、マリア・モンテッソーリによって系統立てられました。
イタリア初の女性医師であったモンテッソーリは、科学的な視点から、子どもをあるがままに客観的に観察しました。
そして、子どもは生まれつき自分自身を成長させる力を備えていると考え、それを助けるための方法を考案しました。
それは、一人ひとりがやりたいことに取り組める環境をつくり、また、子どもが自分一人でできるように援助することでした。
子どもが自分で自分を発達させることで、自分に自信を持ち、自立していけるよう導く教育です。

自分がやりたいことを選ぶ(さくらがおかモンテッソーリスクール) 
本物の包丁で野菜を切る(八幡カトリック幼稚園)
子どもが興味をもつ時期に、自発的に取り組む
モンテッソーリは、0~6歳の子どもは、特定の時期に、ある物事に対して特に興味を持つことを発見しました。
その時期を「敏感期」と呼び、それが表れる物事を「言語」「秩序」「感覚」「運動」「小さいもの」「社会性」といったように分類しました。
そして、それぞれの敏感期に子どもがやりたがる活動を、子どもが自分を高め成長させるものだと捉え、「仕事」と呼びました。
モンテッソーリ教育では、この「仕事」を心ゆくまでできる環境をつくり、子どもが自発的に取り組みます。
教師は、一人ひとりの成長を見極め、個別に援助します。

「数」のおしごと(亀田平和の園保育園) 
教師は個別にサポート(ひばりこどもの家)
自立しながらも協調し合える人間に
3~5歳の仕事は、「日常生活」「感覚」「数」「言語」「文化」という領域に分かれています。
室内には、それぞれの仕事のための様々な「教具」が、整理されて置かれています。
子どもは自分でやりたい仕事を選び、自分のペースで取り組みます。
一方で、子ども同士の関わりや、社会性も大切にされています。
クラスは縦割りで、お互いの仕事を見て興味をもったり、使いたい教具を譲り合ったりします。
身支度・食事・掃除などでも、子どもが中心となり、協力し合って行います。
自立しながらも協調し合える人間を育てることを目指しています。

「言語」の教具の棚(名島保育園) 
お当番さんがお昼の準備(峡南幼稚園)
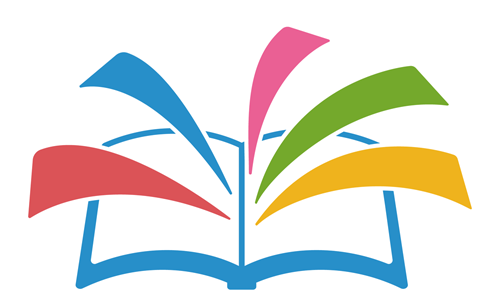 歴史と現在
歴史と現在
マリア・モンテッソーリ(1870-1952年)は、イタリア初の女性医師となったのち、知的障害児の教育に関わりました。
そこで、感覚を使う治療法で大きな成果を上げ、これを健常児に応用することを考えました。
1907年、貧困の子どものための「子供の家」をローマで設立し、さらなる実践ののちに、モンテッソーリ教育法を確立しました。
現在世界117ヵ国以上に広がっており、何らかの形で取り入れている教育機関が、国内で約2千、世界で約2万ヵ所あると言われています。
日本では保育園・幼稚園が中心ですが、欧米では小学校~高校まである学校もあります。
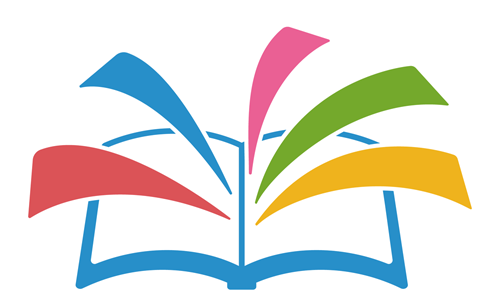 豆知識
豆知識
モンテッソーリ教育では、文字や数を学んだり、自立を促すため、「早期/英才教育」と誤解されることがあります。
実際に、「お受験」のためのような園も存在します。
しかしマリア・モンテッソーリが目指していたものは、何よりも、子ども自身の自立や、世界の平和にありました。
その意志を汲み、大人が求める能力開発のためではなく、あくまで子ども自身を中心とした教育であることを訴える関係者もたくさんいます。
なお、卒業生にAmazonやgoogleの創立者など多くの著名人がいますが、これも、幼い時期から「自分がやりたいこと」を尊重されて育った結果ではないでしょうか。







